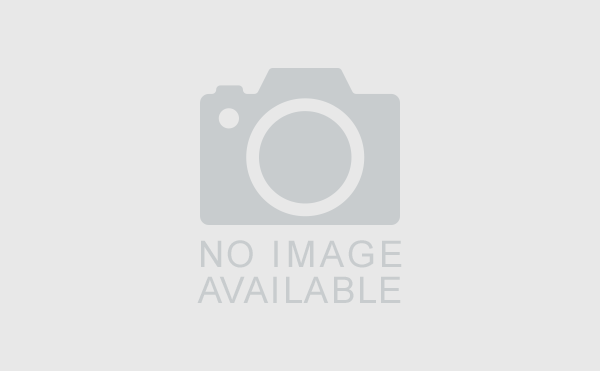生命保険会社の保険計理人の実務基準
2002年1.(3)
「生命保険会社の保険計理人の実務基準」の規定に関する次の①~⑤について、正しいものには○、誤りのあるものには×を付けよ。
- 1号収支分析は標準責任準備金対象外契約の責任準備金についても確認しなくてはならない。
- 1号収支分析を行う期間(分析期間)は少なくとも将来5年間である。
- 1号収支分析は区分経理の商品区分ごとに行う必要があるが、保険計理人が合理的であると判断する場合には、複数の商品区分をまとめて行うことも可能である。
- 1号収支分析は新契約の募集を行う前提(オープン型)でなければならない。
- 1号収支分析の結果が過去の分析の結果と著しく相違する場合は、保険計理人はその原因を附属報告書に記載しなければならない。
解答
- [×:…についても確認しなくてはならない。⇒○:…の一部は確認しなくてもよい。]
- [×:…将来5年間…⇒○:…将来10年間…]
- ○
- [×:…前提(オープン型)でなければならない。⇒○…前提(オープン型)に限らず、すでに締結している保険契約のみで実行する方式(クローズド型)で行ってもよい。]
- ○
1999年1.(3)生命保険会社の保険計理人の実務基準(責任準備金)に関する次の① ~ ⑤について、正しいものに〇、誤っているものに×をつけよ。
- 危険準備金については、区分経理の商品区分毎に積み立てられていることを確認しなければならない。
- 将来収支分析1は原則クローズド型による。
- 将来収支分析の分析期間は必ず10年であり、保険計理人はより長い分析期間を設定してはならない。
- 将来収支分析2では、将来の株式・不動産の価格、為替レート等の変動による損益の発生については考慮しないこととしているから、現在の責任準備金に対応する資産に含み損を抱えており、かつ、分析期間中にその含み損が実現すると見込まれる場合であっても、これを考慮する必要はない。
- 意見書に「不足相当額を最長5年間にわたり、計画的に積み立てる」旨の記載をした場合には、不足相当額の積立計画およびその財源について、附属報告書に記載しなければならない。
2001年1.(2)「生命保険会社の保険計理人の実務基準」の規定に関する以下の①~⑤について、正しいものには〇、誤りのあるものについては×を付けよ。
- 監督当局の認可を得て標準責任準備金(又は平準純保険料式責任準備金)以外の責任準備金を積み立てている場合、1号収支分析では責任準備金積立計画を考慮して責任準備金の確認を行わなければならない。
- 1号収支分析(1号基本シナリオ)において、価格変動準備金、危険準備金の繰人については、原則として、それぞれのリスク量に応じて、法定最低繰入基準を下回らない範囲で、計画的に繰り入れる。
- 1号収支分析において責任準備金不足額が発生しなかった場合、3号収支分析を行う必要は必ずしもない。
- 全件消滅べースの配当所要額の配当可能財源の確認において、「その他有価証券」については含み損益を配当可能財源に算入するが、「満期保有債券」および「責任準備金対応債券」の含み損益は算入しない。
- 配当可能財源の確認に使用する全件消滅べースの配当所要額は、次のとおりである。
全件消滅べースの配当所要額
=(2年目配当契約)翌年度に支払う通常配当(およびこれに準じる配当)
+(3年目配当契約)翌年度に支払う通常配当(およびこれに準じる配当)
+(3年目配当契約)翌々年度に支払う通常配当(およびこれに準じる配当)の1/2
+翌年度に全件消滅したと仮定した場合の消滅時配当
2017年第Ⅰ部1.(3)「生命保険会社の保険計理人の実務基準」に定めるソルベンシー・マージン基準の確認に関する将来収支分析(3号の2収支分析)について、以下の①~⑤の空欄に当てはまる適切な語句または数値を記入しなさい。
・3号の2収支分析は毎年行うものとし、3号の2収支分析を行う期間(以下「分析期間」という。)は、将来[ ① ]年間とする。
・3号の2収支分析のシナリオの各要素は、以下に定める通りとする(このシナリオを「3号の2基本シナリオ」という。)。
◇金利は、直近の長期国債応募者利回りが横ばいで推移するものとする。
◇株式・不動産の価格や為替レートについては、変動しないものとする。
◇[ ② ]の取崩しおよび含み益の実現による積立財源への充当は行わない。
◇価格変動準備金・危険準備金等への繰入れは行わない。
◇劣後性債務・社債・[ ③ ]については、その約定に従って、利息を支払うこととする。
・保険料積立金等余剰部分控除額の下限は、分析期間中の事業年度末に生じた事業継続基準に係る額の不足額の[ ④ ]とする。なお、ソルベンシー・マージン比率の算出を行う日において、保険業法施行規則第69条第5項の規定に基づき積み立てた[ ⑤ ]の額を積み立てていないものとして計算を行う。
2012年第Ⅰ部2.(2)
保険業法に基づく生命保険会社における保険計理人の確認業務の概要について、「生命保険会社の保険計理人の実務基準」を踏まえて、簡潔に説明しなさい。
解答
・保険計理人は保険業法第121条に基づき、毎決算期において以下の確認を行う。
・責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。
-当年度末の責任準備金が法令に従い適正に積み立てられているかどうか。
-将来収支分析(1号収支分析)を行い、将来の資産の状況などを考慮して責任準備金の積立水準が十分であるかどうか。
・契約者配当または社員に対する剰余金の分配が公正かつ衡平に行われているかどうか。
-会社全体で、翌期配当所要額が財源確保されており、健全性を損なわない水準であるかどうか、および翌期の全件消滅ベ-スの配当所要額が財源確保されているかどうか。
-区分経理の商品区分毎に、翌期の全件消滅ベ-スの配当所要額が財源確保されているかどうか。
-契約消滅時に最終精算として消滅時配当を行う保険種類において、代表契約の翌期配当額が原則として当年度末ネット・アセット・シェアを超えていないかどうか、および将来のネット・アセット・シェアが健全性の基準維持のために必要な金額を確保できているかどうか。
・将来にわたり、保険業の継続の観点から適正な水準(事業継続基準)を維持することができるかどうか。
-将来収支分析(3号収支分析)を行い、将来にわたり資産(時価評価)から資産運用リスク相当額を控除した額が、全期チルメル式責任準備金と解約返戻金相当額のいずれか大きい方の額、および負債の部の合計額から責任準備金、価格変動準備金、配当準備金未割当額などを控除した額の合計額を上回っているかどうか。
・保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか。(ソルベンシ-・マ-ジン基準の確認)
-マ-ジンおよびリスクの額が法令の規定等に照らして適正であることを踏まえた上で、ソルベンシ-・マ-ジン比率が200%以上であるかどうか。
-確認においては、将来収支分析(3号の2収支分析)を行い、保険料積立金等余剰部分控除額が下限(分析期間中の事業年度末に生じた事業継続基準に係る額の不足額の現価の最大値)以上であるかどうか。
・保険計理人は、上記確認結果について意見書およびその確認方法などを記載した附属報告書を作成し、取締役会に提出した後、遅滞なく、その写しを内閣総理大臣(実際には金融庁長官)に提出しなければならない。
・保険計理人は、監査役および会計監査人等へ監査を受けるべき計算書類が提出された後、遅滞なく、監査役および会計監査人等に対し、意見書および附属報告書の内容を通知しなければならない。
2008年1.(1)生命保険会社の保険計理人の実務基準における1号収支分析に関し、次の①~⑤の空欄にあてはまる最も適切な語句を記入しなさい。
1号収支分析の結果、責任準備金不足相当額が発生した場合において、保険計理人は、以下の経営政策の変更により、責任準備金不足相当額の一部または全部を積み立てなくてもよいことを、意見書に示すことができる。ただし、これらの経営政策の変更は、ただちに行われるものでなくてはならない。
イ.一部または全部の保険種類の[ ① ]の引き下げ
口.実現可能と判断できる[ ② ]の抑制
ハ.[ ③ ]の見直し
二.一部または全部の保険種類の[ ④ ]の抑制
ホ.今後締結する保険契約の[ ⑤ ]の引き上げ