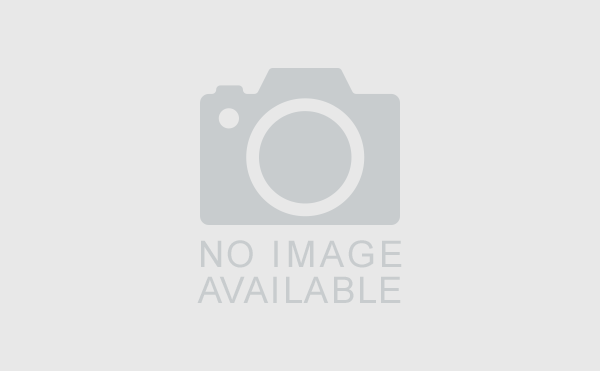第3章 契約者配当
3.1. 序文
3.2. 生命保険会社の利益と契約者配当
3.2.1. 生命保険会計と一般事業会社の利益の違い
3.2.2. 契約者配当は何故行うか
3.2.2.1. 安全性の原則
3.2.2.2. 経験料率の採用
3.2.2.3. 保険料率の調整
3.2.2.4. 競争上の手段として
3.2.2.5. 購買力の実質的価値保全
3.2.3. 経営の技術課題と契約者配当
3.2.3.1. 長期性に基づく収益構造の理解
3.2.3.2. 剰余の適正配分
3.2.3.3. 公平性と実務負荷のバランス
3.2.3.4. 商品・価格政策
3.2.3.5. 多様化する収支構造の把握
3.2.4. 決算利益と契約者配当財源
3.2.4.1. 決算利益の特性からの留意点
3.2.4.2. 契約者配当の特性からの留意点
3.2.5. 契約者配当財源の決定要因
3.2.5.1. 責任準備金評の評価方法
3.2.5.2. ソルベンシー確保
3.2.5.3. 契約者配当の安定性維持向上
3.2.5.4. 通常配当と特別配当
3.3. 保険業法における契約者配当の位置付け
3.3.1. 保険相互会社
3.3.1.1. 保険業法第55条
3.3.1.2. 保険業法第55条の2
3.3.1.3. 保険業法施行規則第30条の2
3.3.1.4. 相互会社における契約者配当原理
3.3.2. 保険株式会社
3.3.2.1. 保険業法第114条
3.3.2.2. 保険業法施行規則第62条
3.3.2.3. 契約者配当と株主配当
3.3.3. 公正かつ衡平について
3.3.3.1. 公正について
3.3.3.2. 衡平について
3.3.3.3. 保険計理人の実務基準における取扱い
3.3.3.4. 決算における配当財源決定に際しての留意点
3.3.4. 無配当保険
3.3.4.1. 無配当保険の意義
3.3.4.2. 1972年のアクチュアリー会建議書
3.3.4.3. 無配当保険の利益の取り扱い
3.4. 生命保険会社の保険計理人の実務基準
3.4.1. 保険計理人の確認業務の導入
3.4.2. 実務基準における契約者配当の確認
3.4.2.1. 基本的な考え方(第17、18条)
3.4.2.2. 会社全体の配当可能財源の確認(第19~21条)
3.4.2.3. 商品区分単位の配当可能財源の確認(第22条)
3.4.2.4. 当年度末アセット・シェアの確認(第24条)
3.4.2.5. 将来のアセット・シェアの確認(第25条)
3.5. 契約者配当の割当と分配
3.5.1. 契約者配当の割当と分配の違い
3.5.1.1. 契約者配当の割当
3.5.1.2. 契約者配当の分配
3.5.2. 契約者配当の分配原則
3.5.2.1. 公平性
3.5.2.2. 弾力性
3.5.2.3. 実務面の簡明性
3.5.2.4. 契約者の理解
3.5.3. 契約者配当の分配方式
3.5.3.1. 契約者配当の分配に関する規定(規則第30条の2)
3.5.3.2. 利源別配当方式
3.5.3.3. 経験料率方式
3.5.3.4. アセット・シェア方式
3.5.3.5. ファンド方式
3.5.4. 契約者配当の割当方式
3.5.4.1. 契約者配当と利益の対応期間(事業年度式と保険年度式)
3.5.4.2. 配当開始期(3年目配当と2年目配当)
3.6. 通常配当
3.6.1. 契約者配当の割当と分配の仕組み
3.6.1.1. 有効継続中の契約に対する割当(1号割当)と分配
3.6.1.2. 消滅契約に対する割当(2号割当)と分配
3.6.2. 利源別配当方式
3.6.2.1. 利差配当
3.6.2.2. 危険差配当
3.6.2.3. 費差配当
3.6.2.4. その他の要素
3.6.3. 調整配当
3.6.3.1. 保険料の遡及低料
3.6.3.2. 契約者配当による事後調整
3.7. 特別配当
3.7.1. 特別配当の考え方
3.7.1.1. アセット・シェアに基づくとする考え方
3.7.1.2. 単にキャピタルゲインの還元とする考え方
3.7.1.3. 経営上の政策配当とする考え方
3.7.2. 1974年のアクチュアリー会答申
3.7.2.1. 消滅時配当(μ配当)
3.7.2.2. 長期継続配当(λ配当)
3.7.2.3. μ配当とλ配当の推移
3.7.3. べスティング
3.7.4. インカム配当原則の見直し
3.7.4.1. インカム配当原則とは
3.7.4.2. アセット・シェア方式による総合収益の還元
3.8. 5年ごと配当保険
3.8.1. 開発の背景
3.8.2. 基本的な仕組み
3.8.3. 割当と分配
3.8.4. 消滅契約に対する分配
3.8.5. 財源準備と割当・分配の関係
3.8.6. 予定利率と契約者配当
3.8.7. 5年ごと配当の課題
3.8.7.1. 契約者の受取実感
3.8.7.2. 事前準備と契約者説明
3.8.7.3. 実務負荷
3.9. 団体保険
3.9.1. 団体保険における配当の割当・分配
3.9.2. 団体保険における配当還元方式について
3.9.2.1. 利源別配当方式
3.9.2.2. 団体保険の契約者配当の要素
3.9.2.3. 団体保険の配当率設定
3.9.2.4. 団体保険の配当課題
3.10. 団体年金保険
3.10.1. 配当体系
3.10.2. 基本的な配当方式
3.10.3. 配当率設定の考え方
3.10.3.1. 1995年頃まで
3.10.3.2. 1996年頃から
3.11. 配当金支払方法
3.11.1. 現金による支払い
3.11.2. 次回払い込む保険料と相殺して支払う
3.11.3. 一時払い保険金買増
3.11.4. 利息をつけて積立てる方法(積立配当)
3.11.5. 一年定期保険買増
3.11.6. 純粋生存買増の問題
3.12. わが国の契約者配当の史的発展
3.12.1. 第2次世界大戦前(~1945)
3.12.2. 第2次大戦後から保険審議会の開催まで(1948~1958)
3.12.3. 配当率の個別化の進展と内部留保の充実(1959~1970)
3.12.4. 特別配当の導入とその発展(1971~)
3.13. 金利低下期における契約者配当について
3.13.1. 1986年の特別問題研究会
3.13.2. 近年の低金利対応
3.13.2.1. 予定利率別の配当基準利回りの導入
3.13.2.2. 契約単位配当方式の導入
3.14. 契約者配当のその他問題点
3.14.1. 募集資料記載の配当率
3.14.2. 個人保険と団体保険のバランス
3.14.3. その他の課題
3.15. (参考)各国の契約者配当制度
3.15.1. 米国
3.15.1.1. 契約者配当理論の見直し
3.15.1.2. 米国における契約者配当の問題点
3.15.2. 英国
3.15.2.1. 契約者配当の歴史
3.15.2.2. 金利低下後の契約者配当のあり方
3.15.2.3. 募集資料に使用する契約者配当率(金融サービス法に関連して)
3.15.3. (旧)西ドイツ
3.15.3.1. 剰余金の分配
3.15.3.2. 分配方法
3.15.3.3. 契約者配当金の支払方法
3.15.3.4. 将来に支払われる配当例示
3.15.4. フランス”Revalorization”の概念について
3.15.4.1. 基本的仕組
3.15.4.2. 保険料据置の選択
3.15.4.3. 料率と責任準備金
3.15.4.4. その他の事項