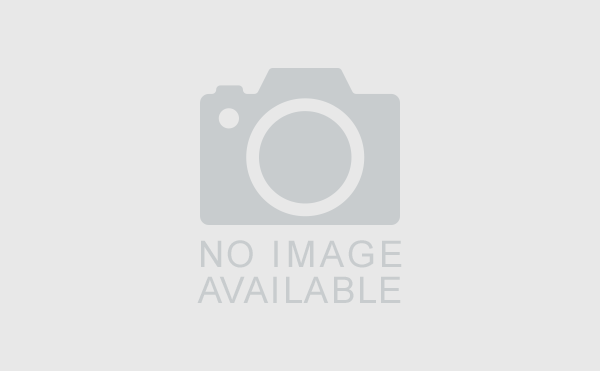第1章 生命保険会計
1.1. 生命保険会計の意義と特徴
過去問
2017年第Ⅱ部3.(1)①
生命保険会計の意義および特徴について簡潔に説明しなさい。
2015年第Ⅰ部2.(1)
「生命保険会計の意義」および「生命保険会計の特徴(保険期間の超長期性から生じる特徴、群団性から生じる特徴、保険料構成要素の多様性等から生じる特徴)」について、簡潔に説明しなさい。
2006年1.(6)
生命保険会計の特徴である「保険期間の超長期性」および「群団性」について、それぞれ簡潔に説明せよ。
2002年2.(1)①
生命保険会計の意義および特徴について説明せよ。
1996年3.(2)
生命保険会計の意義と特徴について述べ、その上で、生命保険会計の中で、アクチュアリーの果たすべき役割について所見を述べよ。
1989年Ⅱ.1.
生命保険会計の特徴である「保険期間の超長期性」「群団性」について説明せよ。
1.1.1. 生命保険会計の意義
生命保険会計とは、生命保険会社の支払能力の状況、業績あるいは活動の実態等を金銭で評価し、会計の言葉で表現することである。
生命保険会社の会計は、保険業法に特別の規定があり、保険会社の健全性を確保することで契約者の保護に重点を置いたものとなっている。
一般会社の会計は、株主や債権者の保護に重点を置いたものである点で、生命保険会計と異なる。
なお、契約者保護に重点を置いた会計は、期間損益を把握する場合など、目的が異なる場合は適切ではなく、別の会計基準を設けている諸外国もあるものの、日本では保険業法に定められる会計が唯一の法定会計である。
分量的に最も多い、2015年の模範解答は以下のとおり。(太字は、特に重要と考えられるポイント)
生命保険会計とは、生命保険会社の支払能力の状況、業績あるいは活動の実態等を金銭で評価し、会計の言葉で表現することである。
生命保険会社においても会社法および企業会計原則等に則った会計処理を行うという点では一般の会社と変わりはないが、契約者保護の観点から生命保険会社の健全化を図るための特別の規定が保険業法にある。
一般の企業会計においては、債権者および投資家の保護に力点が置かれたものになっているが、生命保険会計においては、契約の全期間にわたり契約者保護が確実に遂行されるよう生命保険会社の支払能力確保を重視した会計が指向されている。
また、世界的傾向として、特に生命保険株式会杜の場合、財務会計として一般企業と同じ尺度での比較が求められているが、わが国では保険業法による会計が唯一の法定のものである。
生命保険会計は、この保険業法による会計だけで生命保険会社の全ての情報を表現できる訳ではない。例えば、一般の事業会社・金融機関等と活動の実態が大きく異なること、計算基礎率の妥当性並びに配当率の妥当性および公平性といった面にも充分スポットを当てた表現が必要となること、また商品についても、契約期間の超長期性、群団性および技術性等多くの特殊性を有しているため、保険業法による会計の尺度のみでは適切な評価をすることが難しく、独自の原則・尺度および技術等が要請される。
1.1.2. 生命保険会計の特徴
2002年の解答では、生命保険の特性として教科書から、以下の5点を挙げているが、他の年度では見られないことから、暗記の必要性は薄い。
- 保険期間が超長期であること
- 保険料計算等の前提として大数の法則にしたがう群団が必要なこと
- 保険料の構成要素が多様であること、また平準純保険料方式をとっていることから特に責任準備金の評価において技術的要素が極めて強いこと
- 相互会社形態の会社もあること
- 1,000万件以上の契約を保有する会社もあり契約の量が極めて多いこと
1.1.2.1. 保険期間の長期性から生じる特徴
生命保険会社は、超長期にわたって適正な支払能力を確保することが要請されているため、資産評価の保守性と支払準備のための準備金の充実という特性が生じることになる。
支払準備のための準備金は将来の状況を慎重に予測して評価する必要があり、毎期の支払能力の評価によって、剰余(利益)が異なり、真の剰余(利益)は群団の消滅まで確定しないこともある。
分量的に最も多い、2015年の模範解答は以下のとおり。(太字は、特に重要と考えられるポイント)
一般事業会社では、一般に仕入から販売まで短期間で完結するために週・月単位で損益の測定が可能であるが、生命保険契約は契約の全期間を通じて生じる一定の偶発事故に対して保険給付の支払を約しており、契約期間は超長期にわたる。生命保険会社は超長期にわたって適正な支払能力を確保する必要があり、この点から資産評価の保守性と支払準備のための準備金の充実という特徴が生じる。
資産評価の方法は、支払能力確保の観点からは、不測の事態においても保険給付を行いうるという点で、清算価値が望ましい。
支払準備のための準備金の充実を図るという点から、期間損益を明確にさせることが必ずしも可能ということにならない。支払準備のための準備金は、将来の状況を慎重に予測して評価する必要があり、この結果当期の費用(準備金への繰入額)は通常の方式による費用の評価とは大きく異なることもありうる。
支払準備のための準備金のうち、大宗を占めるものが責任準備金であり、これら準備金が負債の部の大部分を占めていることや、これらの計算の評価性も生命保険会計の特徴と言える。
支払能力の確保と期間損益の把握は表裏の関係にあり、支払能力の評価により期間損益の評価(剰余)も異なる。真の剰余は群団の消滅まで確定しない。
1.1.2.2. 群団性から生じる特徴
保険制度は、大数の法則を前提としている。このことは、保険契約というものは群団として捉えるべきであることを意味している。
保険制度は、一定の群団を目的ごとに設定し、群団間の公平性を図りつつ、支払能力の確保を図っている。期間損益の適正化および税務等の要請から、個々の契約に注目した経理処理が求められているが、特に責任準備金の評価において、群団性を前提とした解釈をすることが必要である。
分量的に最も多い、2015年の模範解答は以下のとおり。(太字は、特に重要と考えられるポイント)
保険制度は大数の法則を前提としており、目的毎に一定の群団を設定し、群団間の公平性を図りつつ、支払能力の確保を図っている。
期間損益の適正化および税務等の要請から個々の契約に注目した経理処理が求められることもあるが、特に責任準備金の評価においては、この群団性を前提とした解釈をすることが必要である。
契約件数が極端に少ない場合、群団として成立させることには無理があり、他の保険に統合する等の工夫が必要である。
事業費は契約初年度と次年度以降で水準が大きく異なるため、収益・費用の対応を目的とした会計では、新契約の世代毎に群団を分け、チルメル式等の考慮を行うこともある。しかし、収益・費用の対応を目的とした会計であっても、世代をまたいだ1つの群団として維持・管理する場合は必ずしもこの種の調整を行う必要はなく、世代間で一種の相互扶助を行いながら支払能力の確保を図っていると解釈される。
1.1.2.3. 保険料構成要素の多様性等から生じる特徴
保険料の計算基礎は3つの要素(予定死亡率、予定利率、予定事業費率)であり、しかも平準保険料方式を採用していることから、収益である保険料を費用に対応させる方法を様々に考えることができる。
分量的に最も多い、2015年の模範解答は以下のとおり。(太字は、特に重要と考えられるポイント)
一般的に、保険料計算基礎には3つの要素(予定利率、予定死亡率、予定事業費率)があり、平準保険料方式を採用している。
この前提から、収益である保険料を費用に対応させる方法は様々に考えることができるが、それぞれの方法は、いずれも一定の目的に応じたものであり、普遍的に正しい方法がある訳ではない。
生命保険会社の剰余は損益計算書において知ることができるが、経営目的からも保険会社を監督する立場からも単に会社全体の剰余を知るだけでは不十分である。多様な計算基礎率の妥当性や契約者配当の公平性等を確認するためにも、剰余を利源別に分析することが必要となる。
その他
保険契約の長期性、支払能力の確保等の特性を考慮した上で、毎期の剰余をどのように評価するかは非常に重要な課題である。これには、保険数理の技法が強く要請されるが、これはアクチュアリーの大きな職務の一つである。
1.1.3.アクチュアリーの職務
(教科書に直接的な記載はないものの)上述した生命保険会計の意義および特徴に鑑み、アクチュアリーの果たすべき役割については、以下のように考えられる。(1996年)
- 適切な責任準備金の評価
「保険会社は、毎決算期において、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなけらばならない。」(保険業法第116条★★)
1.2. 生命保険会計の意義と特徴
1.2.1. 保険料
過去問
2023年第Ⅰ部問題2(1)
保険料の会計的特徴は生命保険会計の特殊性の大きな要因の1つである。収益としての保険料がもつ特徴的な側面を4つ挙げ、それぞれ簡潔に説明しなさい。
2014年第Ⅰ部問題2(1)
生命保険会社における保険料の収益計上基準について、以下の点に触れながら簡潔に説明しなさい。
・保険料未収時の会計上の取扱い(責任準備金の「限度積立」を含む)
・払込期月前に払い込まれた保険料の会計上の取扱い
2000年問題1.(1)次の①~⑤を適切な語句で埋めよ。
いわゆる責任準備金の「限度積立」の一般的な計算は以下のとおりである。責任準備金は、年度末[ ① ]に対して[ ② ]の到来した保険料についてはすべて収入のあったものとして計算し、そこから[ ③ ]中の保険料積立金および未経過保険料相当分を各々差し引いて算出する。ただし、決算時から[ ④ ]末までの期間内に保険料の収入が見込まれない契約についての当該期間に対する[ ⑤ ]相当額は、保険料の収入が見込まれない契約からも死亡保険金請求はあると考えて、これを加えることとしている。
解答
①有効契約(保有契約等も可) ②払込期日 ③未収保険料 ④猶予期間 ⑤危険保険料
1998年問題1.(1)次の①~⑤の文章のうち、正しいものに○、誤っているものに×をつけよ。
- 責任準備金の「限度積立」にかかる実際の計算は、年度末有効契約に対して払込み期日の到来した保険料につき、すべて収入があったものとして計算し、そこから未収保険料中の保険料積立金を差し引いて算出する。
- 次年度以降の保険料を前納した場合、その前納保険料に対して、決算時に損益計算書に計上する責任準備金繰入額は、前納保険料残高の利息による増加分から当事業年度中に充当した保険料を差し引いた額に等しい。
- 下記のような契約が事業年度末直前において解約の申し出があり、解約処理を行ったが、事業年度末現在、解約返戻金は未払いの状態であったので、解約返戻金から契約者貸付金を差し引いた1,100千円を支払備金に計上した。
死亡保険金10,000千円、解約返戻金1,200千円、契約者貸付金100千円- 契約変更の場合の経理処理で、契約者貸付金のない場合の払済保険への変更や、契約転換で被転換契約の責任準備金のうち転換後契約の責任準備金に充当する部分については、経理処理を行わない。
- 決算では収入保険料と保有契約および責任準備金の3者は相互に完全に対応していなければならない。
解答
- ✕…保険料積立金→保険料積立金および未経過保険料相当分
- ○
- ✕…1,100千円→1,200千円(支払備金は、契約者貸付がある場合でも、貸付金を控除する前の金額を計上する。)
- ○
- ○
1989年Ⅰ.5.
責任準備金の「限度積立」について簡潔に説明せよ。
1.2.1.1. 会計上の特性
2023年の模範解答は以下のとおり。(太字は、特に重要と考えられるポイント)
○群団を前提として設定されていること
- 保険料は、算出の根拠となる保険数理上の要請から群団を前提として設定されており、保険料の収益性は一種の評価であって保険金等の特定の費用と個別的な対応関係をもたない。
- 個々契約の保険料は群団として負担すべき金額を分担したものにすぎず、各契約者が一定期間に負担した保険料と、特定の保険金等の支払との間に個別的な対応関係はない。
○責任準備金繰入を通じ、実質的に当期相当分のみを収益計上すること
- 保険料算出上の前提及び保険料収納時の一括収益計上性を考慮すれば、対応する費用として「責任準備金繰入」の計上が不可欠である。
- 責任準備金は支払能力確保の観点から(必ずしも保険料とは同一ではない計算基礎に基づき)評価・積立され、会計上はその期始・期末残高の差を「責任準備金繰入」として費用計上する。
- この「責任準備金繰入」により、収納した保険料を全額収益として計上することに対する一種の調整を行うこととなり、概念的には保険料の当期収益部分相当額を収益として計上することと同様の効果となる。
○保険料の増加が単年度剰余の比例的増加をもたらさないこと
- 付加保険料部分は、対応する費用との間に時間的なずれが存在し、剰余への貢献は遅れる。
- 貯蓄保険料部分は、会計上預り金的な性格を有し、収入時の剰余には貢献しないが、その運用にかかる収益と負債利子に相当する予定利息との差が毎年剰余として計上される。
- 危険保険料部分は、地震等の大災害の発生を除けば、剰余にほぼ比例的な貢献をする。
- 社員配当/契約者配当により、保険料が実質的に事後調整されることがある点も踏まえる必要がある。
○現金主義で計上した上で、決算処理により実質的に発生主義へ調整すること
- 収納した保険料は現金主義に基づき収益計上する。すなわち、前納保険料等の当期に充当される分以外の保険料も、収納した時点で全額を保険料として計上する。
- この場合、翌年度以降に充当される部分は事業年度末に未経過保険料として責任準備金に加算して積み立てることにより、収益と費用との対応を図っている。
- このように保険料は必ずしも収益とならない部分についても全て保険料とし計上し、逆に払込期日が到来しても実際に保険料が払い込まれない場合には、保険料として計上することはない。
- つまり、日々の取引においては現金主義によっており、事業年度末の決算処理により実質的に発生主義と同じ効果となるよう調整を行っている。
1.2.1.2. 収益計上基準
2014年の模範解答は以下のとおり。(太字は、特に重要と考えられるポイント)
保険料の計上は、保険業法施行規則において次のとおり現金主義によるものと規定している。
「決算期までに収入されなかった保険料は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。」
保険料の計上を、入金を手がかりとして行おうとする意図は、保険料の債権としての位置づけにあると思われる。つまり、保険料の支払いは契約者の自由意志に基づくものであり、未収保険料は保険会社の確定債権とはいえないと考えられるため、払込期日の到来等により収益として計上することは保守主義の原則の観点から妥当ではないと考えられる。ただし、債権としての保険料のこうした性格から、入金をもって収益の実現として捉え、収益計上基準は実現主義によると考えても差し支えないであろう。この意味で、企業会計原則における一般の収益計上基準に沿うものであると解釈できるだろう。(保険料未収時の会計上の取扱い)
保険料の計上は現金主義によっており未収保険料は計上しないが、これに対応し、責任準備金の積立ても保険料の入金を限度として行っている。これを責任準備金の「限度積立」と呼んでいる。限度積立にかかる実際の計算は一般に次のとおりである。
責任準備金は、技術上の問題から年度末有効契約に対して一応払込期日の到来した保険料につき、すべて収入のあったものとして計算し、そこから未収保険料中の保険料積立金および未経過保険料相当分を各々差し引いて算出する。
ただし、決算時に保険料が未収となっている契約のうち、保険料払込猶予期間末までに保険料の収入が見込めない契約からも死亡保険金等の請求だけはあると考えて、決算時から保険料払込猶予期間末までの期間に対する危険保険料相当額を未経過保険料として積み立てることとしている。
1.2.1.3. 払込期月前収入の保険料及び前納保険料等
2014年の模範解答は以下のとおり。(太字は、特に重要と考えられるポイント)
(払込期月前に払い込まれた保険料の会計上の取扱い)
払込期月前に払い込まれた保険料は、全額保険料として計上する。ただし、翌事業年度に払込期月を迎える部分については、事業年度末において未経過保険料として責任準備金に積み立てることにより、期間損益の適正化を行う。
1.2.1.4. 保険料の区分
1996年1.(1)⑤
決算では収入保険料と保有契約および責任準備金の3者は相互に完全に対応していなければならない。
ここで言う「相互に完全に対応」とは、ある契約について、収入保険料の計上の有無、保有契約の計上の有無、責任準備金の計上の有無は一致するということである。
1.2.2. 保険契約上の支払い
過去問
2000年1.(4)以下の①~⑤のうち、正しいものには〇を、誤りのあるものには✕を記入せよ。
- 保険金、給付金、解約返戻金等で、支払義務が発生したが何らかの事情で事業年度末に当該事由に対する支払がなされていない場合には、会社はその金額を支払備金として積み立てなければならない。
- IBNR備金の積立額の具体的な計算方法は、次の平均額である。
- 前年度末IBNR備金×当年度支払額+前年度支払額
- 前々年度末IBNR備金×前年度支払額+前々年度支払額
- 前々々年度末IBNR備金×前々年度支払額+前々々年度支払額
- 支払義務が発生して消滅する契約において、死亡保険金が支払備金に計上される場合、この契約に対する責任準備金を計上する必要はないが、年度末の保有契約として計上する必要がある。
- 支払備金は、契約者貸付がある場合には、貸付金を控除した金額を計上する。
- 支払備金は、支払事由発生日以降、所定の利息をつけて積み立てる必要がある。
解答
- ○
- ✕
- ✕…保有契約として計上する必要はない
- ✕…貸付金を控除しない金額を計上する。
- ✕…支払備金については保険給付の支払事由発生日以降、利息を生じさせない。
1.2.2.1. 費用計上基準
保険金勘定は、保険事故発生時期を問わず、現金主義によって計上を行う。
これだけでは、前年度以前に支払債務が発生した金額の支払や、当年度中に支払債務が発生した金額の未払い分について決算に正しく反映できないことから、年度末に支払備金勘定で発生主義に調整を行う。
保険契約上の支払に含まれる勘定科目は、「保険金」「年金」「給付金」「解約返戻金」および「その他返戻金」であり、決算期に監督当局に提出する資料では、保険金については、死亡・災害・高度障害・満期・およびその他の区分を、給付金については、死亡、入院・手術、障害・生存・一時金、およびその他の区分により、細分することが要請されている。
上記のうち、「その他返戻金」とは、「保険金」「年金」「給付金」「解約返戻金」の諸勘定に属さないものを計上する科目であり、前納契約が消滅した場合の前納残高の返還金、前払保険料の未経過分の返還金等を処理するものである。
1.2.2.2. 契約変更の場合の経理処理
契約者貸付金がない場合、商品間で責任準備金の移転が発生するものの、会社全体として責任準備金額に変更がないことから、経理処理は行われない。
契約者貸付金がある場合は、その支払処理を行うことになる。
1.2.2.3. 支払備金
過去問
2022年第Ⅰ部問題1.(3)
(ア)A社の発生年度別・報告年度別の入院給付金支払データ(下表)中の計数のうち、X-1事業年度末における既発生未報告の入院給付金に該当する計数の合計額は(a)百万円である。
(単位:百万円)
発生年度
報告年度X-4
以前X-3 X-2 X-1 X 合計 X-3 10,000 210,000 - - - 220,000 X-2 5,000 10,000 215,000 - - 230,000 X-1 2,000 3,000 15,000 220,000 - 240,000 X 0 1,000 3,000 6,000 240,000 250,000 合計 17,000 224,000 233,000 226,000 240,000 - (イ)B社の医療保険(給付は入院給付金のみ)のデータ(下表)に基づく、X事業年度末におけるIBNR備金積立額は(b)百万円である。
(単位:百万円)
事業
年度保険料等の
収入額給付金の
支払額保有契約の
入院給付金
日額の合計IBNR備金
積立所要額支払備金
(IBNR備金
以外)X-4 276,300 219,000 872,520 7,884 11,121 X-3 283,050 225,000 871,960 8,190 12,251 X-2 289,800 237,500 884,350 8,740 11,357 X-1 300,150 240,000 791,075 9,216 13,436 X 315,400 250,000 808,741 - 9,823 (※)表中の「保有契約の入院給付金日額の合計」、「IBNR備金積立所要額」および「支払備金(IBNR備金以外)」は、事業年度末における数値。
(ウ)IBNR備金については税務上、(c)保険または消費者信用団体生命保険についてのみ、次の算式により計算した金額を限度として損金の額に算入する。
\[\left( \array{当該事業年度に支払事由の発生\\の報告を受けた前事業年度発生\\の保険事故に係る支払備金積立\\所要額}\right) \times \frac{8.3}{100} \times \frac{当該事業年度の被保険者数}{前事業年度の被保険者数}\]
2015年第Ⅰ部問題1.(6)
ある生命保険会社のX事業年度末における既発生未報告支払備金(IBNR備金)積立額を下表に基づき計算し、解答欄に記入しなさい。
ただし、計算過程においては端数処理を行わず、解答においては百万円未満を四捨五入して百万円単位とする。なお、記載のない項目は考慮する必要はない。
事業年度 保険料等の収入額 保険金等の支払額 保有契約高 IBNR備金積立所要額 IBNR備金積立額 X 480,000 250,000 40,000,000 X – 1 420,000 240,000 36,000,000 4,536 4,436 X – 2 390,000 230,000 35,000,000 4,186 4,357 X – 3 360,000 225,000 30,000,000 4,140 4,251 (※)表中の「保有契約高」、「IBNR備金積立所要額」および「IBNR備金積立額」は、事業年度末における数値
1998年1.(6)
A生命保険会社のX事業年度末における既発生未報告支払備金(IBNR支払備金)を下表に基づき計算せよ。計算過程で百万円未満は四捨五入し、百万円単位で求めよ。
事業年度 保険料等の
収入額保険金等の
支払額責任準備金 支払備金
(IBNR以外)IBNR支払備金
積立所要額X 700,000 500,000 4,000,000 20,000 - X-1 667,000 477,000 3,815,000 19,100 9,000 X-2 644,000 460,000 3,670,000 18,400 8,700 X-3 629,000 449,000 3,592,000 18,000 8,500 X-4 614,000 438,000 3,504,000 17,600 8,300 X-5 592,000 422,000 3,376,000 17,000 8,000
1996年1.(3)
保険業法施行規則第73条(支払備金の積立て)および保険業法施行規則第72条(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)について説明せよ。
1996年の過去問では、支払備金について以下のとおり説明している。
保険業法施行規則第73条★★は、保険会社が毎決算期に支払備金として、「保険契約に基づいて支払業務が発生した保険金等(当該支払業務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額」および「第72条に規定する保険金等についてその支払のために必要なものとして計算した金額」を積み立てなければならないことを規定している。
保険業法施行規則第72条★★は、保険業法第117条★★で支払備金を積み立てなければならない「保険契約に基づいて支払業務が発生したものに準ずるもの」について、「保険金、返戻金その他の給付金であって、決算期において、保険会社が、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認められるもの(いわゆるIBNR)」と規定している。
IBNR備金の積立額の具体的な計算方法は、平成10年大蔵省告示第234号★★に規定されており、
- 前年度未IBNR備金積立所要額 ×当年度支払額÷前年度支払額
- 前々年度末IBNR備金積立所要額 ×当年度支払額÷前々年度支払額
- 前々々年度末IBNR備金積立所要額 ×当年度支払額÷前々々年度支払額
支払備金については、保険給付の支払事由発生日以降、利息を生じさせず、契約者貸付金についても解約処理日以降無利息で貸付金勘定に残すこととしている。
1.3. 保険契約準備金
1.3.1. 責任準備金の意義と特徴
過去問
2021年第Ⅱ部3.(1)①
責任準備金の評価における「長期性による特徴」責任準備金の評価における「長期性による特徴」、「基礎率の評価性」について説明「基礎率の評価性」について説明しなさいしなさい。
2013年第Ⅰ部2.(1)
生命保険の責任準備金の評価における「長期性による特徴」および「基礎率の評価性」について、それぞれ簡潔に説明しなさい。また、計算基礎率をロック・インとする方式とロック・インとしない方式(ロック・フリー方式)を比較した場合のロック・インとする方式のメリットおよびデメリットについて、簡潔に説明しなさい。
2010年2.(3)
責任準備金の評価における特徴のうち、「生命保険の長期性」および「責任準備金の群団性」について、簡潔に説明しなさい。
2004年4.(1)①
責任準備金の評価における「長期性による特徴」「基礎率の評価性」について説明せよ。
1999年2.(1)
①責任準備金の評価における、「生命保険の長期性による特徴」、「群団性」、「基礎率の評価性」を説明せよ。
②責任準備金評価の視点の一つに「相当程度の確度で保険契約上の債務を将来に亘り遂行できるか」があるが、この「相当程度の確度」の考え方およびその確度を高める方策について所見を述べよ。
1.3.1.1. 責任準備金の定義・目的
1.3.1.2. 会計の目的に応じた責任準備金
1.3.1.3. 生命保険の長期性による特徴
2021
・生命保険契約の長期性により、責任準備金は、会計の目的に応じて評価されるものである。例えば、長期の現価計算の利率に何を用いるか、死亡率をいかに評価するかといった問題があり、これにより、責任準備金の評価の内容・水準は異なることになる。
・評価に幅があることから、会計方式により責任準備金の評価は異なる。契約者保護を主眼とする業法会計においては、保守的な負債額の確定が主目的であり、その結果として剰余は企業活動の価値や投下資本からのリターンが考慮されにくい面がある。一方、期間損益の把握を主目的とした会計においては、毎年の剰余を適切に算出するのに適した責任準備金の評価を行うこととなる。
2010
生命保険は、期間の数十年に渡る長期の契約であることに大きな特徴がある。したがって、将来の長期間における支払義務に対する、利率、死亡率による不確定性(条件付き債務)、などの「評価」をしなければならず、その会計の目的に応じて、評価の内容・水準は全く異なった結果となる。
たとえば、契約者保護を主眼とした業法会計においては、保守的な負債額の確定が主目的である。また、期間損益の把握を主目的とした会計での責任準備金は、将来の保険金支払いのための債務であることを外れて、毎年の剰余を適切に算出するための調整結果に過ぎないケースさえある。
2004
・生命保険契約の長期性により、責任準備金は、会計の目的に応じて「評価」されるものである。例えば、長期の現価計算の利率に何を用いるか、死亡率をいかに評価するかといった問題があり、これにより、責任準備金の評価の内容・水準は異なることになる。
・評価に幅があることから、会計方式により責任準備金評価は異なる。契約者保護を主眼とする業法会計においては、保守的な負債額の確定が主目的であり、その結果として剰余は企業活動の価値や投下資本からのリターンが考慮されにくい面がある。一方、期間損益の把握を主目的とした会計における責任準備金では、毎年の剰余を適切に算出するのに適した評価を行うこととなる。
1999
・生命保険契約の長期性により、責任準備金は、会計の目的に応じて「評価」されるものとなる。例えば、長期の現価計算の利率に何を用いるか、死亡率をいかに評価するかといった問題があり、これにより、責任準備金の評価の内容・水準は異なることになる。
・評価に幅があることから、会計方式によって責任準備金評価は異なることになる。契約者保護を主眼とした、保険業法に基づく会計においては、保守的な負債額の確定が主目的であり、その結果として剰余は企業活動の価値や投下資本からのリターンというものが考慮されにくい面がある。一方、期間損益の把握を主目的とした会計における責任準備金では、毎年の剰余を適切に算出するのに適した評価を行うこととなる。
※単に「長期だから保守的」とする解答が見受けられたが、これでは不可とした。長期性による特徴は評価が生じることであり、保守的かどうかは評価をどうするかという問題である。きちんと考えが整理されているかに着眼した。
(「保守的」に言及する場合には、長期性ゆえに評価に幅が生じ、支払能力の確保を重視すると(幅のある中で)保守的な評価ーーというように論理だてて記述することが求められる。)
1.3.1.4. 責任準備金の群団性
2013
・生命保険契約の長期性により、責任準備金は、会計の目的に応じて評価されるものである。例えば、長期の現価計算の利率に何を用いるか、死亡率をいかに評価するかといった問題があり、これにより、責任準備金の評価の内容・水準は異なることになる。
・評価に幅があることから、会計方式により責任準備金の評価は異なる。契約者保護を主眼とする業法会計においては、保守的な負債額の確定が主目的であり、その結果として剰余は企業活動の価値や投下資本からのリターンが考慮されにくい面がある。一方、期間損益の把握を主目的とした会計においては、毎年の剰余を適切に算出するのに適した責任準備金の評価を行うこととなる。
2010
責任準備金は「群団」を前提とした概念であり、銀行預金のように個々の契約毎に分割された責任準備金という負債があるということではない。全契約の合計額(又は保険種類等何らかの群団毎の合計額)を、その群団のための支払能力確保のため積み立てるということであり、個別契約毎に分解されるものではない。
すなわち、大数の法則が成立しうる保険群団に対して、支払能力の確保という観点を重視し、アクチュアリーは事業年度末において責任準備金の評価を行うわけである。たとえば、契約件数が極端に少ない場合、群団として成立させることには無理があり、他の保険に統合する等の工夫が必要である。
世代間をまたぐ群団性について考えた場合、生命保険の運営にかかる事業費は初年度(新契約費)と翌年度以降で水準が異なるため、収益・費用の対応を目的とした会計では、新契約の各世代毎に群団を分け、チルメル式等の考慮を行うこともある。
最終的には責任準備金積立ては支払能力確保を目的として行われることから、世代間の一種の相互扶助を行いながら積み立てることになり、個別契約単位に分解することはできない。
なお、事業費面以外でも、投資年度別の収益把握法をとらない場合の利率面、選択効果により世代間の死亡率が異なる場合等についても、群団で考える必要がある。
1999
・責任準備金は「群団」を前提とした概念であり、個別契約ごとに分解されるものではない。極端な例として、契約が1件しかない場合、これに対する責任準備金として「保険金額×責任準備金率」を準備するだけでは、将来の保険金支払に備えたことにはならない。この例から、責任準備金は、個別契約ごとに分解されるものではなく、大数の法則が成立しうる保険群団に対して、全体として評価を行うものであることが理解される。契約件数が極端に少ない場合には群団として成立させることには無理があり、他と統合する等の工夫が必要である。
・事業費は初年度と翌年度以降で水準がまったく異なるが、世代間をまたいだひとつの群団として把握する場合には、世代間の一種の相互扶助を行いながら積み立てることになり、この意味からも個別契約単位に分解できない。投資年度別の把握をしない場合の利率面、選択効果により世代間の死亡率が異なる場合等についても、群団で考える必要がある。
1.3.1.5. 基礎率の評価性
2021
・責任準備金は、将来の支払能力確保という観点から評価されることから、その計算基礎率は、必ずしも保険料計算基礎率と同一ではない。例えば、現時点で将来の保険事故発生率が高くなることが相当に確実であると予想されるなら、その見込まれる発生率を考慮することが必要であろう。
2013
・責任準備金は、将来の支払能力確保という観点から評価されることから、その計算基礎率は、必ずしも保険料計算基礎率と同一ではない。例えば、現時点で将来の保険事故発生率が高くなることが相当に確実であると予想されるなら、その見込まれる発生率を考慮することが必要であろう。
2004
・責任準備金は、将来の支払能力確保という観点からr評価」されることより、その計算基礎率は、必ずしも保険料計算基礎率と同一ではない。例えば、現時点で将来の保険事故発生率が高くなることが相当に確実であると予想されるなら、その見込まれる発生率を考慮することが必要であろう。
1999
・責任準備金計算用の計算基礎率については、将来の支払能力の確保という観点から「評価」を行うこととなり、必ずしも保険料計算基礎率と同一の率で 平価するわけではない。また、例えば、現時点において将来の保険事故発生率が高くなることが相当に確実であると予想されるならば、その見込まれる発生率を考慮することが必要であろう。
1.3.1.6. 相当程度の確度
1999
「相当程度の確度」の考え方
・生命保険の特徴である長期性により、100%の確率で将来の保険金支払を保証することはできない。このため、ある程度以上の確度でしか支払能力は担保できないが、その確度をどの程度とするのかが重要であり、責任準備金評価に際しては「相当程度の確度」を確保する視点が求められる。(ただし、確率を明示的な水準で設定することはできない。)
「相当程度の確度」を高める方策
・責任準備金の評価を保守的に行うこと。
基礎率について、変動や将来の悪化の可能性を考慮して、保守的に設定することが考えられる。また、積立方式についても、保守的な方式を用いることが考えられる。
ただし、会計上の制約から、この方策単独で確度を高めることは困難である。・責任準備金評価用基礎率を契約時に固定(LOCK-IN)せず、各評価時点において定めた基礎率を既契約にも適用することが考えられる。
LOCK-IN方式に立つ場合であっても、例えば、将来の運用利回りが恒常的に旧の責任準備金評価利率を下回り、保険料中のバッファーでそれを吸収できないことが見込まれるときは、新の責任準備金評価利率を適用するか、または、不足額を別の形(不足責任準備金)で準備する必要があろう。
キャッシュフロー・テストにより、資産負債の両面から検証を行うことも有効である。・相当程度の確度を、責任準備金とそれ以外のソルベンシー・マージンとで役割分担させ、より支払い能力を強化すること。
ある程度の環境変化は責任準備金で対応するものの、それ以上の環境変化はソルベンシー・マージンで対応するという考え方である。ソルベンシー・マージンを充実させることにより、「責任準備金+ソルベンシー・マージン」をもって角度を高める。(全般的に、ポイントを的確にとらえ、明確に記述することが求められる。)
1.3.1.7. 責任準備金の「会計」上の意義
1.3.2. 保険業法における責任準備金
過去問
1996年3.(1)
標準責任準備金制度の目的およびその概要について説明し、標準責任準備金制度導入による生命保険会社経営への影響について所見を述べよ。
1998年1.(2)標準責任準備金の対象外の契約に関する以下の表の①~⑤を適当な語句または数値で埋めよ。
対象外の契約 積み立てるべき金額 ・変額保険 [ ① ]の収支残 ・[ ② ]のない契約
・責任準備金・保険料の計算基礎率を変更できる旨、約款に規定している契約
・予定死亡率以外の保険事故率を[ ④ ]計算基礎として用いる契約
・保険期間[ ⑤ ]年以下の保険契約
・外国通貨をもって保険金、返戻金その他の給付金の額を表示する保険契約
・新保険業法施行前に締結した契約保険料及び責任準備金の算出方法書で認可された予定利率及び予定死亡率その他の保険事故率を基礎として[ ③ ]により計算した金額
2001年2.(1)①
標準責任準備金制度の目的および概要について、説明せよ。
2003年1.(1)標準責任準備金の対象外の契約に関して以下の空欄を埋めよ。
対象外の契約 積み立てるべき金額 ・責任準備金が[ ① ]に属する財産の価額により変動する保険契約 [ ① ]の収支残 ・[ ② ]及び払戻積立金を積み立てない保険契約
・責任準備金・保険料の計算基礎率を変更できる旨、約款に規定している契約
・保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約
・保険期間[ ③ ]年以下の保険契約
・[ ④ ]をもって保険金、返戻金その他の給付金の額を表示する保険契約
・平成8年3月31日以前に締結された契約保険料及び責任準備金の算出方法書で認可された予定利率及び予定死亡率その他の保険事故率を基礎として[ ⑤ ]により計算した金額
2009年1.(1)標準責任準備金の対象外契約(平成17年4月1日以降に締結する保険契約)に関し、以下の①~⑤の空欄に当てはまる最も適切な語句または数字を記入しなさい。
- 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約であって、保険金等の額を[ ① ]していない保険契約
- [ ② ]及び払戻積立金を積み立てない保険契約
- [ ③ ]において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約[ ③ ]において、当該保険契約の締結時の標準責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を[ ① ]している保険契約を除く。)
- 保険期間が[ ④ ]年以下の保険契約(注)
- [ ⑤ ]をもって保険金、返戻金その他給付金の額を表示する保険契約
(注)積立勘定を設置して、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に係る責任準備金の金額に相当する財産の全部又は一部をその他の財産と分別して運用している保険契約については、保険期間が10年以下の保険契約
2017年第Ⅰ部1.(1)標準責任準備金の対象外契約(平成17年4月1日以降に締結する保険契約)について、以下の①~⑤の空欄に当てはまる適切な語句または数字を記入しなさい。
以下のいずれかに該当する契約は、標準責任準備金の対象外契約である。
- 責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約であって、保険金等の額を[ ① ]していない保険契約
- [ ② ]及び払戻積立金を積み立てない保険契約
- [ ③ ]において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約([ ③ ]において、当該保険契約の締結時の標準責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を[ ① ]している保険契約を除く。)
- 保険期間が[ ④ ]年以下の保険契約(注)
- [ ⑤ ]をもって保険金、返戻金その他給付金の額を表示する保険契約
(注)積立勘定を設置して、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に係る責任準備金の金額に相当する財産の全部又は一部をその他の財産と分別して運用している保険契約については、保険期間が10年以下の保険契約
2019第Ⅰ部2.(1)
標準責任準備金制度の目的および概要について、簡潔に説明しなさい。なお、概要については今後新たに締結する保険契約に対して適用される制度のみを解答すればよい。
2006年1.(2)保険業法施行規則第69条(生命保険会社の責任準備金)について、以下の空欄を埋めよ。
第六十九条(生命保険会社の責任準備金)
生命保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した[ ① ]を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
一 [ ② ]
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、[ ③ ]に基づき計算した金額(第二号の二の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
二 [ ④ ]
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、決算期において、まだ経過していない期間をいう。次条及び第二百十一条の四十六において同じ。)に対応する責任に相当する額として計算した金額(次号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
二の二 払戻積立金 (省略)
三 危険準備金 (省略)
2~5(省略)
6 第一項第三号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
一 第八十七条第一号に掲げる保険リスクに備える危険準備金
二 同条第二号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
三 同条第二号の二に掲げる[ ⑤ ]に備える危険準備金
7(省略)
1.3.2.1. 旧保険業法上での位置付け
1.3.2.2. 保険業法改正の経緯
1.3.2.3. 責任準備金の内訳
1.3.2.4. 標準責任準備金の原則
2019
<目的>
〇1996年4月に保険業法が改正され、商品・価格の自由度がより高まり、競争が促進されるようになった。
〇ただし、実質的な価格は事後に確定する保険の性格から、確固たる健全性確保の仕組みを併せて構築しておかなければ、却って消費者保護が図れなくなる可能性がある。
〇このため、保険会社の健全性を高め、支払能力を確保する視点から、長期の保険契約で内閣府令で定めるもの(標準責任準備金対象契約)については、内閣総理大臣(金融庁長官に委任)が責任準備金の積立方法、計算基礎率水準について必要な定めを行うことができるとした、所謂「標準責任準備金」制度が設けられた。
<概要>
〇標準責任準備金制度とは、内閣府令で定める「長期の保険契約」(標準責任準備金対象契約)について、金融庁長官が「責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準」について必要な定めをすることができる、というもの。
〇標準責任準備金の対象外の契約(平成17年4月1日以降に締結する保険契約)
・責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約であって、保険金等の額を最低保証していない保険契約
・保険料積立金及び払戻積立金を積み立てない保険契約、保険料積立金を計算しない保険契約
・保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約(保険約款において、当該保険契約の締結時の標準責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証している保険契約を除く。)
・保険期間が1年以下の保険契約
・外国通貨をもって保険金、返戻金その他給付金の額を表示する保険契約
〇責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準
・積立方式は、平準純保険料式
・予定死亡率は、公益社団法人日本アクチュアリー会が作成し、金融庁長官が検証したもの(生保標準生命表2018(死亡保険用)、生保標準生命表2007(年金開始後用)または第三分野標準生命表2018)。ただし、当該予定死亡率以外の予定死亡率を責任準備金の計算の基礎として用いることが適当であると認められる保険契約を除く。
・予定利率は、保険料の払方や契約特性に応じて「第1号保険契約」、「第2号保険契約」、「第1号保険契約及び第2号保険契約以外の契約」に分けて設定された計算方式により定まる。
・第三分野商品の予定発生率、予定解約率など、共通の定めのない基礎率についても、制度の主旨に鑑み、保守的な設定が望まれる。
・契約時の評価基礎率を用いて評価するロックイン方式である。
・計算した保険料積立金の額が契約者価額を下回る場合には、契約者価額を保険料積立金とする。
・特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約については、一般勘定の責任準備金は、原則として、一般勘定における最低保証に係る保険金等の支出現価から一般勘定における最低保証に係る純保険料の収入現価を控除する標準的方式により算出した額とする。ただし、標準的方式により計算される責任準備金の債務履行を担保する水準と同等であることが認められる場合は、標準的方式に替えて、代替的方式を使用することができる。特別勘定の責任準備金は収支の残高とする。
・生命保険会社の業務又は財産の状況および保険契約の特性等に照らし特別の事情がある場合には、標準責任準備金を下回る積み立てが認められている。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
2001
① 標準責任準備金制度の目的および概要について、説明せよ。
<目的>
〇1996年4月の保険業法の改正により、商品・価格の自由度をより高め、競争を促進する方向
○ 規制緩和・自由化・競争促進の一方で、確固たる健全性確保の仕組みの構築
〇契約者保護
○ 保険会社の健全性を高め、支払能力を確保
<概要>
○ 標準責任準備金の対象外契約 施行規則第68条
・1996年4月1日以前契約
・責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約
・保険料積立金および払戻積立金を積み立てない保険契約、ならびに保険料積立金を計算しない保険契約
・保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約(標準利率を超える利率を最低保証する保険契約を除く。)
・その他法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となる係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
→ 平成13年金融庁告示第24号
・いわゆる損害保険契約(第2分野商品)
・保険期間が1年以下の保険契約
・外国通貨を持って保険金、返戻金その他給付金の額を表示する保険契約
(対象外契約の積立方式・予定利率等にも触れるのが望ましい。)
○ 標準責任準備金の積み立て方式および計算基礎・・・ 平成8年大蔵省告示第48号
・積立方式:平準純保険料式
・予定死亡率:社団法人日本アクチュアリー会が作成し、金融庁長官が検証したもの [標準死亡率: 現在は「生保標準生命表1996」]
・予定利率: 過去の10年国債応募者利回りを基準とした計算方式の概要等 [標準利率: 現在は1.50%]
・計算した保険料積立金の額が契約者価額を下回る場合には、当該契約者価額をもって保険料積立金とする。
・計算基礎はロックイン
・生命保険会社の業務又は財産の状況および保険契約の特性等に照らし特別の事情がある場合には、標準責任準備金を下回る積み立てが認められている。…… 施行規則第69条第4項第4号
1996
標準責任準備金制度の目的
今後、規制緩和、自由化等の流れの中で保険商品が多様化、複雑化する一方、資産運用リスク等が増大していくものと見込まれる。他方、これまでの保険料率、配当に関する規制は順次緩和する必要がある。このように変化する環境の中で、これまで負債の大宗を占め、保険金等の支払に充当されてきた保険会社の責任準備金についてもその在り方を再検討することが必要となった。
具体的には、これまでは生命保険会社については健全性を最も重視した純保険料式(平準式)による責任準備金の積立が中心になっていたが、純保険料式による積立であっても、例えば予定利率が高い場合には責任準備金の積立は薄くなることから、予定利率の適切な設定やソルべンシー・マージンの充実と併せて健全性を維持する必要があるとの指摘を受けるようになった。
そこで、(1)生命保険会社の支払能力の向上、(2)規制緩和、競争促進、(3)保険制度における国際的な調和を図ることを目的として、標準レベルを設定する標準責任準備金の考え方を導入するとともに、この標準責任準備金については当面は純保険料式による積立を標準とした上で、積立方式や計算基礎率に弾力性を持たせることとした。
標準責任準備金制度の概要
①標準責任準備金の対象契約
標準責任準備金の対象契約は、保険業法施行規則第68条において、(新)保険業法施行以降に締結する保険契約で、次のいずれにも該当しない保険である。
一、責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約
二、保険料積立金を積み立てない保険契約
三、保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してある保険契約
四、その他法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約
②標準責任準備金の積立方式および計算基礎
標準責任準備金の積立方式および計算基礎は、大蔵大臣告示第48号において、以下の通り規定されている。
一、積立方式は、平準純保険料式とする。
二、予定死亡率は、社団法人日本アクチュアリー会が作成し、大蔵大臣が検証したものとする。
三、予定利率は2.75%とする。
標準責任準備金制度導入による生命保険会社経営への影響
①保険会社の健全性の確保
(a)責任準備金の充実
これまでは、大蔵省令により、生命保険会社については健全性を最も重視した純保険料式(平準式)による責任準備金の積立てが原則になっていたが、純保険料式による積立であっても、例えば、予定利率が高い場合には責任準備金の積立は薄くなる。
今般、標準責任準備金制度が導入されたことにより、責任準備金の積立方式のみならず、計算基礎率(予定利率、予定死亡率)についても、標準となる水準を、大蔵省告示に規定され、これまで以上に、責任準備金の積立の充実が図られるようになる。
(b)責任準備金積立の弾力化
標準責任準備金の積立方式や計算基礎率等については、これまで以上に肌目細かく規定しつつ、一方で、それぞれの生命保険会社の実態(業務又は財産の状況及び保険契約の特性)により、標準責任準備金を下回る積立てでも、支払能力を維持できる場合には、大蔵大臣の認可を得て、標準責任準備金を下回る積立ても認められることとなった。また、一方、生命保険会社の実態から、標準責任準備金を上回る積立(追加責任準備金の積立)が必要な場合には、大蔵大臣への届出を行った上で、これを積み立てることができることとなり、それぞれの生命保険会社の実態に合わせた弾力的な責任凖備金積立が可能となった。
従って、今後、生命保険会社は、それぞれの会社の実態を把握した上で、責任準備金の積立について、判断を行うことが必要となる。
(c)保険計理人の役割の高まり
上記のように、責任準備金積立が弾力化される一方、保険業法第121条により、保険計理人は、「責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか」を確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならないこととなった(さらに、その写しを大蔵大臣に提出しなければならない
すなわち、生命保険会社が、支払能力を維持し、契約者利益を保護していく上での、保険計理人の役割がこれまで以上に高まったと言える。
(d)保険料と責任準備金の計算基礎率の分離
標準責任準備金制度の導入に伴い、保険料と責任準備金の計算基礎率が必ずしも一致しないこととなる。
例えば、保険料の予定利率を、標準責任準備金の評価利率より高い水準に設定した場合、その生命保険会社は、責任準備金(=標準責任準備金)の積立てに際して、これまで以上の財源を要することとなり、保険料の設定等においては、れまで以上に慎重な検討が必要となった。
(e)税制への影響(責任準備金の損金算入限度の拡大)
これまでは、「保険料の計算基礎率に基づき、平凖純保険料式で計算した責任準備金」が損金算入限度であったが、税制の改正により標準責任準備金が、新たな損金算入限度となった。すなわち、税制面においても、支払能力の向上が容易になったと言える。
②規制緩和・競争促進
現在、保険料率については、適正な保険料率の設定、契約者間の公平性確保、事業の健全性維持等の観点から、「保険料及び責任準備金の算出方法書」の変更に際して、大蔵大臣の認可が必要とされている。
しかし、今後の保険料率規制の在り方としては、(1)契約者間の公平性等の原則の法令化が図られ、(2)ソルべンシー・マージン基準の導入、区分経理及び特別勘定の導入・活用、ディスクロージャーの拡充、生命保険事業における標準責任準備金の考え方やアセット・シェア方式の導入等により、適正な保険料率設定が確保でき、契約者保護等の面で問題が少ないと判断される分野については、認可制を緩和し、届出制に移行することが考えられる。
また、配当の承認制については、アセット・シェア方式の導入、区分経理及び特別勘定の導入・活用、ディスクロージャーの拡充、ソルべンシー・マージンや
標準責任準備金の考え方導入等が行われたことから、平成8年度決算から、承し、制が廃止された。
以上のように、標準責任準備金の導入により、保険会社の支払能力が向上し、契約者利益の保護が図られることから、これまで認可制・承認制であったものを、届出制に移行する等、規制緩和が進められることとなる。その結果、生命保険会社の保険料率や配当の設定は、自由化・個別化が進み、会社間の競争も促進されることとなる。
③国際的な調和
米国では、生命保険会社の商品・保険料率・配当等が自由化されているが、方で、標準責任準備金法により、責任準備金の積立方式、予定利率、予定死亡率等が法定され、また、保険計理人が、責任準備金の積立水準等について、評価する仕組みを取り入れており、標準責任準備金制度の下で、生命保険会社の支払能カ確保、契約者利益の保護を図っている。
英国でも、生命保険会社の商品・保険料率・配当等は自由化されているが、従来から、責任準備金の積立方式・予定利率等についてルール化され、保険計理人が、責任準備金の積立水準等について、評価する仕組みとなっている
さらに、EC第3次指令では、EC域内各国に対して、それぞれの保険法に定める、責任準備金の積立方法(予定利率の設定等)をルール化する一方、各国政府は、保険監督において、保険料率等を規制することを禁じている。
今般、わが国の保険業法において、標準責任準備金制度を導入したことは、うした国際的な潮流に則したものであり、今後、諸外国との交流(例えば、わが国の生命保険会社の諸外国への進出、諸外国の生命保険会社のわが国への参入等)が、一層進められると考えられる。
1.3.2.5. 標準責任準備金対象外の契約等
1.3.2.6. 追加責任準備金
1.3.2.7. 届け出制
1.3.2.8. 再保険
1.3.3. 責任準備金の実務
1.3.3.1. 責任準備金の実務的な計算方法
1.3.3.2. 責任準備金の実務的な経理処理
1.3.4. 実際の責任準備金の評価方法
1.3.4.1. 責任準備金評価の前提となるもの
1.3.4.2. 各種の責任準備金評価方式
1.3.4.2.1. 平準純保険料式責任準備金
1.3.4.2.2. チルメル式責任準備金
1.3.4.2.3. 初年度定期式責任準備金
1.3.4.2.4. 営業保険料式責任準備金
1.3.4.2.5. 責任準備金のキャッシュフローテスト
1.3.4.3. 責任準備金評価用基礎率
1.3.5. 財務会計としての責任準備金
1.3.5.1. 責任準備金の負債性
1.3.5.2. 負債としての責任準備金の性質
1.3.5.3. 会計監査人(公認会計士)との関係
1.3.6. 責任準備金以外の各種準備金
過去問
1990年Ⅰ.3.次の語句を簡潔に説明せよ。
危険準備金
2008年2.(1)
危険準備金の意義について簡潔に説明しなさい。また、危険準備金に関し、企業会計上の引当金設定要件との関係について簡潔に説明しなさい。
2017年第Ⅰ部1.(1)平成10年・大蔵省告示第231号に規定されている、危険準備金の取崩基準について、以下の①~⑤の空欄に当てはまる適切な語句を記入しなさい。
(危険準備金の取崩基準)
第六条 危険準備金Ⅰ及び危険準備金Ⅳは、それぞれ[ ① ]がある場合において、当該[ ① ]のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。
2 危険準備金Ⅱは、[ ② ]がある場合において、当該[ ② ]のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。
3 危険準備金Ⅲは、最低保証に係る[ ③ ]が負の場合において、当該[ ③ ]のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。
4 その他前三項それぞれに共通する取崩基準として、前事業年度末の[ ④ ]の額が当該事業年度末の[ ⑤ ]を超える場合は、当該超える額を取り崩さなければならない。
1.3.6.1. 危険準備金
1990
通常の死亡危険とは異なり、保険料計算基礎に変動を及はすであろう異常事態に対処するために、責任準備金のひとつとして積立てられるもの。蔵銀通達により死差益の5%以上を毎年積立てることとされている。ただし、その積立限度は人保険は危険保険金の1/1,000、団休保険は2/1,000となっている。{更に、取崩しの制限、最近の同準備金をとりまく問点について言及する解答もあった。}
2008
危険準備金は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備え、責任準備金の内訳の1項目として積み立てるものである。すなわち、通常の予測の範囲内の危険(変動)は狭義の責任準備金(保険料積立金・未経過保険料)で準備するが、それを超える異常な変動に備えるものとして、危険準備金がある。
危険準備金は、次に掲げるリスクに備え、それぞれ区分して積み立てる。
<危険準備金Ⅰ>
保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険)に備える。
<危険準備金Ⅱ>
予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険)に備える。
<危険準備金Ⅲ>
最低保証リスク(変額保険等で保険金等の額を最低保証するものについて、特別勘定の価額が通常の予測を超える価格の変動等により、最低保証する保険金等の額を下回る危険)に備える。
<危険準備金Ⅳ>
第三分野保険の保険リスクに備える。
危険準備金は、上記のように対応するリスクが明記され、それぞれのリスクに対応した積立基準、積立限度、取崩基準が法令で規定されている。対象とするリスクが現実のものとなる可能性が必ずしも高いとは限らないものもあるため、日本の現在の企業会計上負債性引当金の設定要件を満たさないかもしれないが、特別法上の準備金として整備されていると言えよう。
なお、負債の部に計上できる引当金の設定要件は以下の通り。(企業会計原則注解18)
・将来の特定の費用または損失であること
・その発生が当期以前の事象に起因していること
・当該事象の発生の可能性が高いこと
・その金額を合理的に見積もることができること
1.3.6.2. 価格変動準備金
1.4. 資産運用関係収支
1.4.1. 資産勘定の内容
過去問
2003年1.(4)
責任準備金対応債券について、簡潔に説明せよ。
2004年1.(3)生命保険会社の貸借対照表における有価証券の評価に関し、以下の空欄を適当な語句で埋めよ。
保有目的区分 貸借対照表上の評価基準 評価差額の取扱い ( ① ) 時価 当期の損益として損益計算書に計上 満期保有目的の債券 ( ③ ) 責任準備金対応債券 ( ③ ) 子会社・関連会社株式 ( ④ ) ( ② ) 時価 損益計算書に計上せず、貸借対照表の( ⑤ )の部に計上
2006年1.(4)
保険会社において責任準備金対応債券の取扱いが認められている理由について簡潔に説明せよ。
2012年第Ⅰ部2.(1)
「責任準備金対応債券」の概要について、簡潔に説明しなさい。解答にあたっては、ある小区分でデュレーション・マッチングを満たさなくなった場合の取り扱いについても言及すること。
2017年第Ⅰ部1.(2)
邦貨建債券の保有目的区分(満期保有目的の債券、責任準備金対応債券、その他有価証券)ごとの取り扱いに関して、以下の①~⑤に該当する保有目的区分には○を、該当しない保有目的区分には×をそれぞれ記入しなさい。ただし、過去から当期末にいたるまで時価の変動に伴う簿価の評価替え(減損処理を含む)はないものとし、ヘッジ会計は適用していないものとする。
①貸借対照表において、時価で評価される。
②損益計算書において、時価の変動額が当期純剰余(当期純利益)に影響を与える(ただし、「部分純資産直入法」は採用していないものとする)。
③ソルベンシー・マージン比率の計算において、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額は、ソルベンシー・マージン総額に含まれる。
④ソルベンシー・マージン比率の計算において、価格変動等リスクの計算対象である。
⑤実質資産負債差額の計算において、時価を用いる。
2018年第Ⅰ部1.(2)
責任準備金対応債券を特定するための要件を5つ列挙しなさい。
2023年第Ⅰ部1.(5)
生命保険会社における有価証券の保有目的区分(名称のみ)を「その他有価証券」以外に4つ列挙しなさい。
2024年第Ⅰ部1.(1)
責任準備金対応債券の満たすべき要件について、以下の(a)~(f)の空欄に当てはまる適切な語句または数値を記入しなさい。
○デュレーション・マッチングの有効性の判定と定期的検証
責任準備金対応債券であるためには、小区分毎に特定された保険契約群の責任準備金に対し、保有債券が以下の基準を満たしていなければならない(なお、責任準備金対応債券は当該小区分の(a)の額を超えてはならない。)。また、デュレーション・マッチングを行った結果が、以下の基準の範囲内であることは、定期的に検証しなければならない。
D(L)=k×D(A)(ただし、kは(b)≦k≦(c))
D(L):責任準備金のデュレーション
D(A):責任準備金対応債券のデュレーション
○責任準備金対応債券の範囲
責任準備金対応債券は、(d)要因で時価が変動する債券とし、上記のデュレーション・マッチング等の要件を満たしたものをいう。また、責任準備金対応債券は責任準備金と同一(e)であることを要する。なお、以下の債券は、責任準備金対応債券から除外しなければならない。
①元利金の一部又は全部が責任準備金と異なる(e)建の債券
②発行者の(f)の悪化している債券
③所有目的が他の金融機関との持合いとなっている劣後債券
④デリバティブと組み合わせた債券
1.4.1.1. 現金・預貯金
1.4.1.2. コールローン
1.4.1.3. 買現先勘定
1.4.1.4. 買入金銭債権
1.4.1.5. 商品有価証券
1.4.1.6. 金銭の信託
1.4.1.7. 有価証券
| 保有目的区分 | 定義 | 貸借対照表上の評価基準 | 評価差額の扱い |
| 売買目的有価証券 | 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券 | 時価 | 当期の損益として損益計算書に計上 |
| 満期保有目的の債券 | 満期まで所有する意図を持って保有する社債その他の債券 | 償却原価 | |
| 責任準備金対応債券 | 金利変動に対する債券と責任準備金の時価変動を概ね一致させることにより、責任準備金の金利変動リスクを回避することを目的として保有する債券 | 償却原価 | |
| 子会社・関連会社株式 | 取得原価 | ||
| その他有価証券 | 上記に区分される以外の有価証券 | 時価 | 損益計算書に計上せず、貸借対照表の純資産の部に計上(全部純資産直入法) (注) |
2024
○デュレーション・マッチングの有効性の判定と定期的検証
責任準備金対応債券であるためには、小区分毎に特定された保険契約群の責任準備金に対し、保有債券が以下の基準を満たしていなければならない(なお、責任準備金対応債券は当該小区分の(a)の額を超えてはならない。)。また、デュレーション・マッチングを行った結果が、以下の基準の範囲内であることは、定期的に検証しなければならない。
D(L)=k×D(A)(ただし、kは(b)≦k≦(c))
D(L):責任準備金のデュレーション
D(A):責任準備金対応債券のデュレーション
○責任準備金対応債券の範囲
責任準備金対応債券は、(d)要因で時価が変動する債券とし、上記のデュレーション・マッチング等の要件を満たしたものをいう。また、責任準備金対応債券は責任準備金と同一(e)であることを要する。なお、以下の債券は、責任準備金対応債券から除外しなければならない。
①元利金の一部又は全部が責任準備金と異なる(e)建の債券
②発行者の(f)の悪化している債券
③所有目的が他の金融機関との持合いとなっている劣後債券
④デリバティブと組み合わせた債券
2018
責任準備金対応債券を特定するための5つの要素
・リスク管理を適切に行うための管理・資産運用方針等の策定
・管理・資産運用方針等を遵守する体制の整備
・小区分の設定と管理
・デュレーション・マッチングの有効性の判定と定期的検証
・責任準備金対応債券の範囲
2012
・保険会社の負債の大部分を占める責任準備金は、長期間の債務であっても契約時に固定された予定利率で評価されている。このため、「その他有価証券」として債券等の資産側のみを時価評価した場合は、財務諸表上、純資産の額が大きく変動し、デュレ-ション・マッチングにより資産・負債の金利変動リスクを適切に管理していても、真の財務状況が適切に反映されないおそれがある。
・一方、「満期保有目的の債券」に区分すれば評価額を計上する必要がないが、売却が制限されることから、目標デュレ-ションの達成が困難となる。
・このような事態を避けるため、保険会社には責任準備金対応債券の取り扱いが認められている。
・責任準備金対応債券を特定する要件としては、以下が定められている。
-リスク管理を適切に行うための管理・資産運用方針等の策定
-管理・資産運用方針等を遵守する体制の整備
-小区分の設定と管理
-デュレ-ション・マッチングの有効性の判定と定期的検証
-責任準備金対応債券の範囲
・責任準備金対応債券は、責任準備金の残存年数や保険商品などにより作成された小区分ごとに管理することとされており、その小区分ごとにD(L)=k×D(A)(ただし、0.8≦k≦1.25。ここに、D(L)は責任準備金のデュレ-ション、D(A)は責任準備金対応債券のデュレ-ション)という基準を満たす必要がある。
・責任準備金対応債券は「満期保有目的の債券」と同様、償却原価法で資産評価され、減損の会計処理も適用される。
・債券の発行者の信用状態の著しい悪化や税法上の優遇処置の廃止等に起因する場合を除き、目標デュレ-ション達成以外の目的による責任準備金対応債券の売却、保有目的の変更又は合理的な理由のない小区分の変更が行われた場合には、該当する小区分のすべての責任準備金対応債券を変更時の償却原価をもって、その他有価証券に振り替えなければならない。
・ある小区分でデュレ-ション・マッチングを満たさなくなった場合には、当該小区分に属するすべての責任準備金対応債券を変更時の償却原価をもって、その他有価証券に振り替えなければならない。
・ただし、予期せぬ解約率の大幅な上昇等の合理的に予想ができなかった要因でデュレ-ション・マッチングの基準に適合しなくなった場合には、当該小区分に属するすべての責任準備金対応債券を、変更時の償却原価をもって満期保有目的債券に振り替えることができる。・上記振替を行った場合、振替を行った事業年度を含む二事業年度においては、取得した債券を当該小区分に分類することはできなくなる。また、この間において当該小区分を含む小区分の範囲を変更することはできなくなる。
・責任準備金対応債券を保有している場合は、財務諸表において「責任準備金対応債券に関する時価情報」「リスクの管理方針の概要」等の注記をしなければならない。ソルベンシ-・マ-ジン比率の計算においては、分子(マ-ジン)には含み損益(時価評価額と帳簿価額の差)は算入されない。また、分母(リスク)の価格変動等リスク相当額のリスク係数は1%となっている。
・実質資産負債差額の計算には、責任準備金対応債券と「満期保有目的の債券」の含み損益が算入される。また、ソルベンシ-・マ-ジン比率が0%以上で実質資産負債差額が負の場合であっても、実質資産負債差額から、責任準備金対応債券と「満期保有目的の債券」の含み損益を控除した額が正であり、かつ、流動性資産が確保されている場合には、原則として「保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分」の第三区分の命令(期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令)は発出されない。
2006
保険会社の負債の大部分を占める責任準備金は、長期間の債務であっても契約時に固定された予定利率で評価されている。このため、「その他有価証券」として債券等の資産側のみを時価評価した場合は、財務諸表上、純資産の額が大きく変動し、デュレーション・マッチングにより資産・負債の金利変動リスクを適切に管理していても、真の財務状況が適切に反映されないおそれがある。
一方、「満期保有目的の債券」に区分すれば評価額を計上する必要がないが、売却が制限されることから、目標デュレーションの達成が困難となる。
このような事態を避けるため、保険会社には責任準備金対応債券の取扱いが認められている。
2003
保険会社の財務諸表において、金融商品の時価評価が導入された一方で、責任準備金はロックイン方式で計算されている。このため資産・負債のデュレーションマッチングを図り、資産・負債の金利リスク変動を適切に管理している場合においても、財務諸表上、資本の額が変動し、保険会社の真の財務状況が適切に表されないおそれがある。このため、保険会社が一定の条件を満たした場合に、会計上「責任準備金対応債券」区分を設け、償却原価法に基づく評価及び会計処理を行うことにより、このような事態を避けることができるようになった。
責任準備金対応債券は、
・責任準備金の残存年数や保険商品などにより作成された小区分ごとに管理する
・その小区分ごとに、D(L)=k×D(A)(ただし、kは0.8≦k≦1.25。ここに、D(L)は責任準備金のデュレーション、D(A)は責任準備金対応債券のデュレーション)という基準を満たす
・目標デュレーション達成目的以外に売却は不可能
などの条件を満たす必要がある。
1.4.1.8. 貸付金
1.4.1.9. 有形固定資産
1.4.1.10. 無形固定資産
1.4.1.11. その他資産
1.4.1.12. 繰延税金資産
1.4.1.13. 支払承諾見返り
1.4.1.14. 貸倒引当金
1.4.2. 資産運用収益および資産運用費用
過去問
2012年第Ⅰ部1.(1)生命保険会社の財務諸表の勘定科目に関し、以下の①~⑤の空欄に当てはまる適切な語句を記入しなさい。
・[ ① ]は、相互会社が社員への剰余金分配の額を安定させるために積み立てる任意積立金である。
・支払利息は、借入金、預り保証金、預り金、借入有価証券に対する支払利息、契約関係支出に係る遅延利息等を計上する勘定科目である。なお、据置保険金に関する利息については、支払利息ではなく[ ② ]に計上される。
・日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」が改正(平成23年3月29日付)されたことを受け、従来、特別利益に表示していた[ ③ ]および償却債権取立益は、経常利益に表示することとなった。
・繰延税金資産は、将来減算一時差異および税務上の[ ④ ]に係る税金のうち、将来の会計期間において回収が見込まれる税金額を計上する勘定科目である。
・損失てん補準備金は、相互会社が担保資金を増強し、将来の損失に備えて積み立てる法定準備金であり、株式会社における[ ⑤ ]に相当するものである。
1.4.2.1. 利息及び配当金等収入
1.4.2.2. 支払利息
1.4.2.3. 商品有価証券運用益・商品有価証券運用損
1.4.2.4. 金銭の信託運用益・金銭の信託運用損
1.4.2.5. 売買目的有価証券運用益・売買目的有価証券運用損
1.4.2.6. 有価証券売却益・有価証券売却損
1.4.2.7. 有価証券評価損
1.4.2.8. 有価証券償還益・有価証券償還損
1.4.2.9. 金融派生商品収益・金融派生商品費用
1.4.2.10. 為替差益・為替差損
1.4.2.11. 特別勘定資産運用収益・特別勘定資産運用費用
1.4.3. 資産運用収益・資産運用費用以外の主な資産運用関係収支
1.4.3.1. 固定資産等処分益・固定資産等処分損・不動産圧縮損
1.4.3.2. 保険業法第112条評価益
1.4.3.3. 価格変動準備金繰入
1.4.4. デリバティブ取引の会計処理とヘッジ会計
過去問
2008年1.(3)生命保険会社の資産運用に係る会計に関し、次の①~⑤の空欄にあてはまる最も適切な語句または数字を記入しなさい。
- ・一般勘定における売買目的有価証券以外の有価証券を[ ① ]処理により時価評価した際の評価差額を有価証券評価損に計上する。帳簿価格に対する時価の下落率が約[ ② ]%以上の場合は、回復可能性についての合理的な反証がなければ、「[ ③ ]」に該当し[ ① ]処理する。下落率が約[ ② ]%未満の場合は、個々の企業において合理的な基準を設定し、[ ① ]処理するか否かを判定することになる。
- ・ヘッジ会計の方法には「[ ④ ]ヘッジ」と「[ ⑤ ]ヘッジ」がある。[ ④ ]ヘッジでは、時価評価されたヘッジ手段の損益または評価差額をヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において計上する。[ ⑤ ]ヘッジは、ヘッジ対象である資産または負債に係る損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に認識する方法をいう。
2013年第Ⅰ部1.(2)ヘッジ会計に関する以下の①~⑤の文章について、下線部分が正しい場合は○、誤っている場合は×を記入するとともに、誤っている場合には下線部分を正しい表現に改めなさい。
- ヘッジ取引は、減殺されるリスクにより、相場変動を相殺するヘッジ取引とデュレーションを固定するヘッジ取引の2つに分けることができる。
- ヘッジ対象となる個々の資産または負債が共通の相場変動等による損失の可能性にさらされており、かつ、その相場変動等に対して同様に反応することが予想されている場合は複合へッジを適用することができる。
- 「その他有価証券」をヘッジ対象とするヘッジ取引において認められている会計処理方法は、繰延ヘッジのみである。
- ヘッジ会計の要件を満たしており、想定元本、利息の受払条件、契約期間がヘッジ対象の資産又は負債とほぼ同一であるような金利スワップは、時価評価せずに金銭の受払の純額を当該資産又は負債に係る利息に加減して処理することが認められている。
- ヘッジの有効性については、ヘッジ取引時以降も継続して確認しなければならず、頻度として少なくとも年に1回は有効性の評価を行わなければならない。
2020年第Ⅰ部1.(5)ヘッジ会計に関し、以下の①~⑤の空欄に当てはまる適切な語句または数を記入しなさい。
ヘッジ取引は、デリバティブ等のヘッジ手段を用いて有価証券等のヘッジ対象のリスクを減殺することを目的とするが、減殺されるリスクにより、[ ① ]を相殺するヘッジ取引と、[ ② ]を固定するヘッジ取引の2つに分けることができる。
ヘッジ会計の適用にあたっては、リスク管理に関する内部規程の作成等が前提条件となる。ヘッジ取引時以降の事後テストでは、最低[ ③ ]カ月に1回は有効性の評価を行い、ヘッジ対象の[ ① ]または[ ② ]の変動がヘッジ手段によって高い水準で相殺されたことを確認しなければならない。ここで、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の変動とヘッジ手段の変動の比率がおおむね[ ④ ]%から[ ⑤ ]%の範囲内にある場合は、高い水準で相関があると認められる。
1.4.4.1. 先物取引
1.4.4.2. オプション取引
1.4.4.3. スワップ取引
1.4.4.4. ヘッジ会計
1.4.5. 資産利回りについて
1.4.5.1. ハーディー方式の平均利回り
1.4.5.2. トータルリターン・ベースの利回り
1.5. 資産評価
1.5.1. 生命保険会計としての資産の基準
1.5.1.1. 原価基準(cost basis または historical cost basis)
1.5.1.2. 時価基準(current vaue basis)
1.5.1.3. 低価基準
1.5.1.4. 生命保険会計における資産評価
1.5.2. 時価評価
1.5.2.1. 時価とは何か-市場価値と時価および公正価値
1.5.2.2. 日本における時価基準会計の導入
1.5.3. 減損会計
1.5.3.1. 日本に置ける減損会計の導入
1.6. 利源分析・基礎利益・配当
1.6.1. 剰余金の分配
1.6.2. 実務基準による配当の確認
1.6.3. 社員配当準備金及び社員配当金
1.6.3.1. 社員配当準備金
1.6.3.2. 決算時求められる配当準備金関係資料
1.6.3.3. 社員配当準備金及び社員配当金の経理処理
1.6.4. 利源分析
過去問
1989年Ⅱ.3.
利源分析において、5年チルメル式と平準純保険料式の相違点を述べ、各々の長所・短所について簡単に所見を述べよ。
- 利源分析は、損益計算書から出発し、「予定事業費」「予定利息」等の両建勘定を用い、損益計算書上の各項目を利源別に分解することにより、各利源の損益を評価しようとするものである。
「相違点」…5チル式と純保式では責任準備金の積み方、予定事業貲、予定利息等が異なることにより、各利源の損益が相当異なってくる。通常(新契約比率が一定以上)の場合、純保式は5チル式に比べ、費差損益においては予定出業貸計上が少なくなり剰余が減少(損失が増加) 利洋損益は予定利息が十多くなり剰余が減少(損失が増加)、死損益は、危険保険金額がやや小さくなるため剰余が減少(損失が増加)する。 一方、準関係損益におい(は、実際の積増額との調整が行われるため、当該会社が純保積増を行っている場合、5チル式の利源分析では、その超過積増分が損失となる。また解約益計算においては、積立額と支払額の差が益として計上されるため、益が大きく出る。
「長所・短所」…5チル式の場合、新契約費の支出実態に近い枠設定が出来、新契約の多寡により貲差損益が影響を受けにくいというメリットがある一方、責任準備金を純保式で積立ている会社においては、責準関係損が生じ、費差、死差、利差の合計が合計損益から乖離するといううデメリットがある。純保式の場合は、逆に予定事業贒枠の設定が実態にそくさず、新契約比率が高い年度において貸差損益を圧迫するというデメリットがあるが、純保積立の会においては、責準関係損益の調整が少なくすみ、三利源の損益が比較的正当に評価されるというメリットがある。
{更に、以上の事実を前提とし(、用途に応じた方式の選択、配当財源との関係から現行の利源分析のかかえる問題点等について所見を述べる解答もあった。}